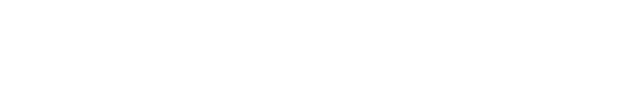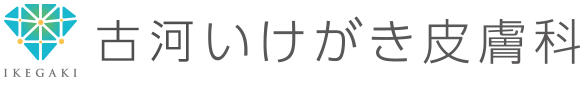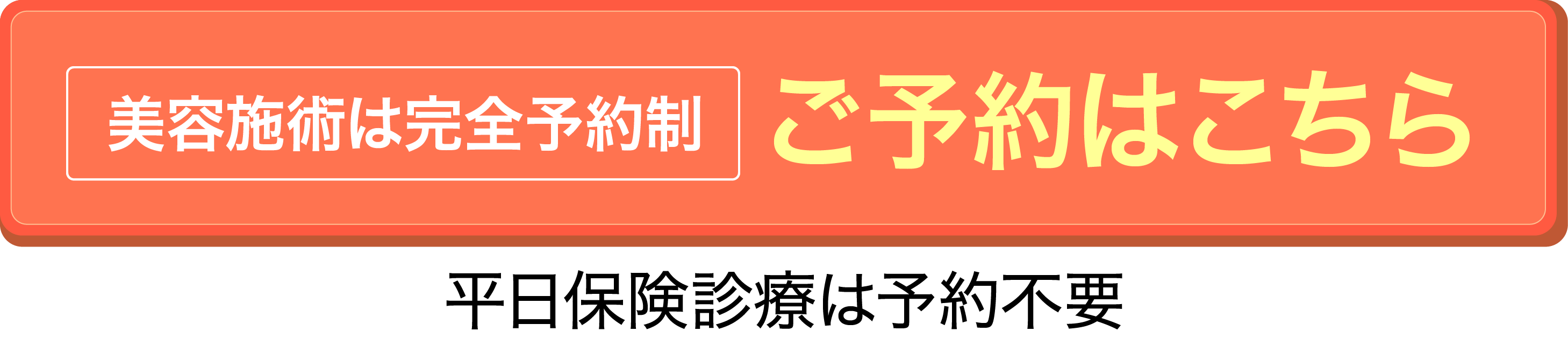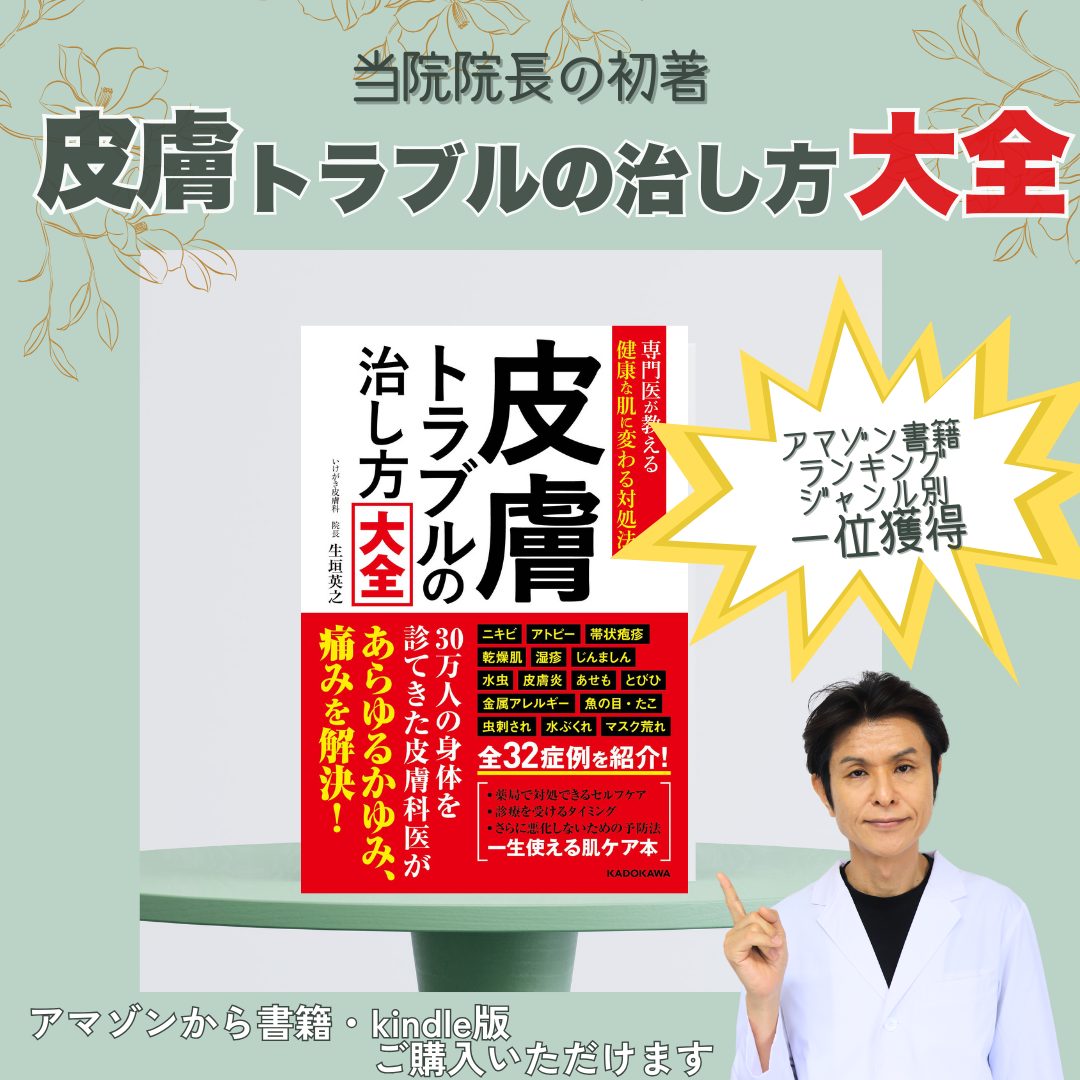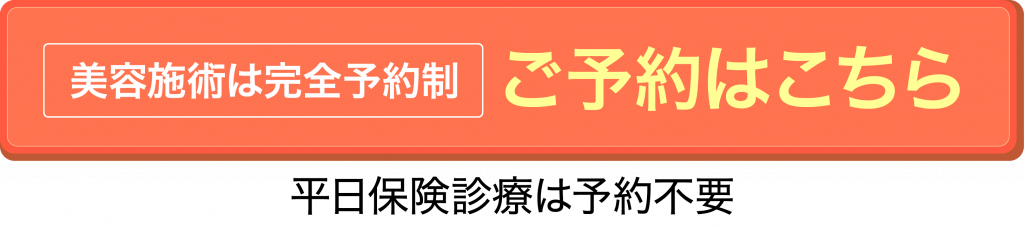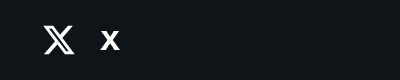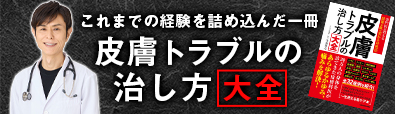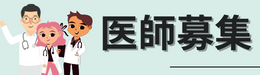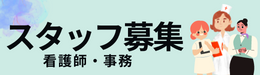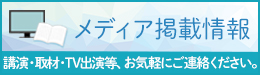マダニに咬まれたら命の危険も?マダニ感染症(SFTS)の真実と予防法

さて、いよいよ夏本番ですね。暑さも増してきて、キャンプや登山、川遊び、BBQなど、自然の中で過ごす機会が増えてくる季節です。お子さんと一緒に野外活動を楽しむご家庭も多いのではないでしょうか。そんな楽しい夏の時間を安全に過ごしていただくために、今回はぜひ知っておいていただきたいことがあります。それが、「マダニ」による感染症のリスクについてです。最近では、テレビやインターネットのニュースでも「マダニ」という言葉を耳にする機会が増えてきました。「マダニ感染症」と呼ばれる一連の病気は、まだあまり知られていない一方で、実際には身近な場所で誰にでも起こりうる感染症の一つです。

マダニは見た目も小さく、草むらや山の中など自然の多い場所にひそんでいます。そのため、知らないうちに咬まれてしまったりする方も少なくありません。症状があまりない事も多く「たかが虫刺されでしょ。」と思い軽く考える方も多いと思いますが、実は命に関わる病気になってしまう事があります。こう聞くと急に怖くなってしまうと思いますが、正しい知識を持ち、ちょっとした工夫で予防することで、マダニによる感染症は予防することができます。 今回は皮膚科医として、マダニとはどういう虫なのか、なぜ注意が必要なのか、咬まれてしまったときにどう対処すればよいのか、そして命に関わる重症感染症についても、不安になりすぎることなく正しく備えられるよう、丁寧に話していきます。このをブログを通じて、「マダニってこわいんだ…」という気持ちよりも、「気をつけておけば大丈夫なんだ」「家族にも教えてあげよう」と思っていただけたらうれしいです。それでは、さっそく始めていきましょう。
今回は皮膚科医として、マダニとはどういう虫なのか、なぜ注意が必要なのか、咬まれてしまったときにどう対処すればよいのか、そして命に関わる重症感染症についても、不安になりすぎることなく正しく備えられるよう、丁寧に話していきます。このをブログを通じて、「マダニってこわいんだ…」という気持ちよりも、「気をつけておけば大丈夫なんだ」「家族にも教えてあげよう」と思っていただけたらうれしいです。それでは、さっそく始めていきましょう。
以下のブログの内容はこちらのYouTubeでも解説しています。良ければごらんください。
マダニってどんな虫?

マダニは、私たちの生活圏のすぐそばにいる、ごく身近な存在です。「山や森の中にしかいない」と思われがちですが、実際には草むらや畑、河川敷、公園の植え込み、さらには自宅の庭先や犬の散歩道などにも生息していて、ちょっとした自然とのふれあいの中で遭遇することがあります。とくにマダニが活発に活動するのは、春から秋にかけての暖かい季節です。この時期は肌の露出も増え、レジャーや旅行で野外に出かける機会も増えるため、マダニに咬まれるリスクも高まります。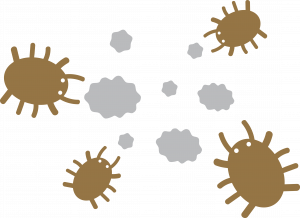 夏休みに入ると、キャンプや登山、川遊びに出かけたあと「子どもがマダニに咬まれていた」「気づいたら自分の足首に黒い点が…」といったご相談が皮膚科にも多くなってきます。マダニの体長は種類によって異なりますが、およそ2〜4mmほどで、吸血していないときはゴマ粒のように小さく、色も茶色や黒っぽくて見つけにくいのが特徴です。しかし、一度皮膚に咬みついて吸血を始めると、数日かけて体が大きくふくらみ、5〜10mmほどの大きさになることもあります。普通のダニや蚊と違って、マダニは皮膚に強くしがみつき、自らの鋭い口器を深く差し込んで固定しながら吸血を続けるという特徴があります。
夏休みに入ると、キャンプや登山、川遊びに出かけたあと「子どもがマダニに咬まれていた」「気づいたら自分の足首に黒い点が…」といったご相談が皮膚科にも多くなってきます。マダニの体長は種類によって異なりますが、およそ2〜4mmほどで、吸血していないときはゴマ粒のように小さく、色も茶色や黒っぽくて見つけにくいのが特徴です。しかし、一度皮膚に咬みついて吸血を始めると、数日かけて体が大きくふくらみ、5〜10mmほどの大きさになることもあります。普通のダニや蚊と違って、マダニは皮膚に強くしがみつき、自らの鋭い口器を深く差し込んで固定しながら吸血を続けるという特徴があります。

咬まれても痛みやかゆみがほとんどないため、咬まれていることに気づかない方も少なくありません。それだけに、「気づいたときには数日経っていた」「すでに体調が崩れていた」というケースもあるため、見落としやすい虫として注意が必要です。実際に、草むらや山道に入ったあと、「ふと見たら足首に黒い点がついていた」「シャワーを浴びたとき、何かついてると思って触ったら脚が動いていてびっくりした」他には、「急にホクロができたので、見てほしい」というのもよくあります。拡大してみるとマダニでびっくりすることもあります。一番記憶に残っているのは、以前自分が総合病院に勤めていたときに、他の科の先生に呼ばれて、「ホクロが動いたので、びっくりして救急外来に来た患者がいるので見てほしい」と言われて行ったら、マダニだった事があり、その先生は、手で触ってしまったといって、手をものすごく消毒していて、さらに虫が苦手だったらしく青い顔をしていましたね。マダニは、「見えないところでゆっくり近づいてくる存在」だからこそ、あらかじめ存在を知っておくこと、予防の意識を持つことが非常に重要なんです。
マダニが怖い本当の理由
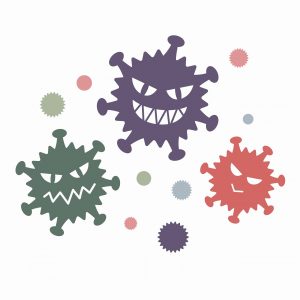
マダニというと、「虫に咬まれる」「皮膚がかゆくなる」といったイメージを持っている方が多いかもしれません。しかし、マダニの本当の怖さは、ただの虫刺されでは済まないところにあります。実は、マダニの中にはウイルスや細菌などの病原体を体内に持っているものがいます。そしてそれが、咬まれた際に人間の体内に入り込むことで、思わぬ感染症を引き起こすことがあるのです。つまり、マダニは“ただ血を吸うだけの虫”ではなく、感染症の媒介者でもあるということ。そのため、「咬まれたあとしばらくしてから体調を崩した」「咬まれた記憶もないのに熱が出た」といったケースも少なくなく、注意が必要です。中でも特に注目されているのが、重症熱性血小板減少症候群、英語だとSevere fever with thrombocytopenia(トロンボサイトペニア) syndromeという長い名前の病気です。英語の頭文字をとってSFTSと言います。このSFTSは、マダニに咬まれたあとに感染する可能性がある病気で、名前に重症とあるだけあって、発症すると非常に重い症状を引き起こすことがあります。

突然の高熱や吐き気、下痢、腹痛、食欲不振、強い倦怠感、血小板が減ることで内出血やあざが出やすくなる、意識が混乱したりするといった症状がでます。しかも、SFTSには現時点で確立された治療薬やワクチンがなく、対症療法が中心となります。つまり、かかってしまうと「すぐ治す方法」がないため、早期発見・早期対応が命を守るカギになるのです。日本国内でも、SFTSの感染報告は最近では毎年100件以上あり、決して珍しい病気ではなくなってきています。しかもその致死率は10〜30%とされており、決して軽く見ていい病気ではありません。 特に高齢の方、持病をお持ちの方、免疫力が落ちている方は、重症化のリスクが高くなります。ちなみに潜伏期間は6日~2週間程度といわれています。このように、マダニによる感染症は、「虫にかまれて気持ち悪い」という問題だけでなく、1週間以降に体の中で大きな異変が起こる可能性があることが一番のリスクなのです。しかし、正しい知識を持っていれば、感染のリスクを大きく下げることは可能です。まずは「なぜマダニに注意しなければならないのか」を知ることが、最も大切な第一歩です。
特に高齢の方、持病をお持ちの方、免疫力が落ちている方は、重症化のリスクが高くなります。ちなみに潜伏期間は6日~2週間程度といわれています。このように、マダニによる感染症は、「虫にかまれて気持ち悪い」という問題だけでなく、1週間以降に体の中で大きな異変が起こる可能性があることが一番のリスクなのです。しかし、正しい知識を持っていれば、感染のリスクを大きく下げることは可能です。まずは「なぜマダニに注意しなければならないのか」を知ることが、最も大切な第一歩です。
もしマダニに咬まれたら

では、もしマダニに咬まれてしまったら、どうすればよいのでしょうか?まず大事なのは、「無理に自分で引きはがさないこと」です。先ほど言ったようにマダニは、ただ皮膚にくっついているのではなく、鋭い口器を皮膚の奥深くに差し込んで、しっかり固定したうえで吸血を行います。このため、無理に引っ張ると口の一部が皮膚の中に残ってしまう可能性があり、それが原因で炎症や感染を引き起こすことがあります。たとえば、赤く腫れたり、膿がたまったり、しこりになったりと、皮膚トラブルが長引くケースも見られます。また、無理に取ろうとしてマダニの体がつぶれてしまうと、病原体が皮膚から体内に入りやすくなる可能性もあるといわれています。咬まれたことに気づいたら、できるだけ早く皮膚科を受診するのが最も安全で確実な方法です。皮膚科では、専用の器具で除去したり、麻酔下に皮膚ごとマダニを切除したりします。その後の皮膚の炎症予防や、必要に応じた抗菌薬の処方も含めて、適切な対応を受けることができます。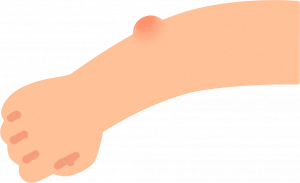 ちなみにマダニを除去する際に皮膚に麻酔薬をうつと、マダニの足が動いたりします。一度経験がありますが、マダニが噛むのをやめて移動してびっくりした事もありました。また、先ほど言ったように咬まれた直後だけでなく、数日〜1週間ほどの体調の変化にも注意が必要です。マダニが感染源となるウイルスや細菌を持っていた場合、数日から2週間の潜伏期間を経て症状が現れることがあります。なので、咬まれたあとの体調変化にも注意し、「発熱」「下痢」「だるさ」などの症状が出たらすぐに医療機関を受診しましょう。ちなみに虫刺されについて、私の書いた本にも書いてありますので、是非読んでみてください。下にリンクを貼っておきます。
ちなみにマダニを除去する際に皮膚に麻酔薬をうつと、マダニの足が動いたりします。一度経験がありますが、マダニが噛むのをやめて移動してびっくりした事もありました。また、先ほど言ったように咬まれた直後だけでなく、数日〜1週間ほどの体調の変化にも注意が必要です。マダニが感染源となるウイルスや細菌を持っていた場合、数日から2週間の潜伏期間を経て症状が現れることがあります。なので、咬まれたあとの体調変化にも注意し、「発熱」「下痢」「だるさ」などの症状が出たらすぐに医療機関を受診しましょう。ちなみに虫刺されについて、私の書いた本にも書いてありますので、是非読んでみてください。下にリンクを貼っておきます。
予防するにはどうすれば?

マダニに咬まれないためには、「そもそも咬まれない工夫=予防」がとても大切です。レジャーや旅行で山や川に行くとき、また庭の草刈りや畑作業のときにも気をつけましょう。予防のポイントは①長袖・長ズボンで肌を露出しない、ズボンのすそを靴下の中に入れるなど、ダニが入り込めない服装にする②虫よけスプレーを活用する。③大切なのが「帰宅後のチェック」。衣類や皮膚、特に首まわり・腕・膝裏・足首など、柔らかい部分にマダニがついていないか確認してください。ペットと一緒に外出した場合は、ペットの身体にもマダニが付いていないか必ず見ましょう。
虫よけスプレーって本当に効くの?

「虫よけスプレーをすれば大丈夫」と思われがちですが、実は100%防げるわけではありません。マダニに対して効果があるとされている有効成分は2つ言われていて、1つはディートという成分です。これは、高濃度でマダニにも一定の効果ありと言われていますが、小さいお子さんに使用する場合は回数制限などあり注意が必要です。もう1つはイカリジンです。これはディートより刺激が少なく、子どもにも使いやすいです。ただし、汗をかいたり、水に濡れたりすると効果が弱まるため、2〜3時間ごとにこまめに塗り直すことが大切です。また、先ほど言ったようにスプレーだけでは完全に防ぎきれないため、服装による物理的な防御が第一です。「スプレーしてるから大丈夫」と油断せず、複数の対策を組み合わせることが重要です。
SFTSは他人事じゃない

SFTSはかつては西日本での報告が中心でしたが、最近では関東や東北地方でも発症例が出ています。私のクリニックのある茨城県でもSFTSの患者が報告されており、私たちの地域でも「他人事ではない」状況になってきました。「私は登山しないから大丈夫」「庭にちょっと出ただけだから平気」と思っている方ほど、油断が命取りになることもあるんです。SFTSは感染者の3割近くが亡くなることもある、非常に深刻な感染症です。自己防衛の意識を持ち、正しい知識と備えを持つことが、命を守ることにつながります。
エンディングまとめ

今回は、マダニとそれに関連する感染症「SFTS」についてお話ししました。今回はSFTSを取り上げましたが、他にもマダニが媒介する感染症は、ライム病や日本紅斑熱など他にもあります。レジャーや旅行が増えるこの季節、楽しい思い出を残すためにも、健康管理と感染症予防はとても大切です。

☑ 草むらや山では服装に注意
☑ 虫よけは過信せず、こまめな塗り直しを
☑ 咬まれたら自己処理せず、早めに皮膚科へ
☑ 少しでも体調がおかしいと思ったら、すぐ受診。
正しく知って、しっかり備えれば、防げるリスクもたくさんあります。ご家族みんなで健康に、楽しい夏を過ごしてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました!